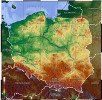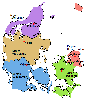ページ: 1 2
モーツアルトが生まれた街、ザルツブルグに行った。ミュンヘンから列車で2時間位であった。ザルツブルグは、塩の町という意味であり、ケルト人が住んでいて塩を発見したという。「赤と黒」や「パルムの僧院」で有名なスタンダールの「恋愛論」には、結晶作用というたとえがある。ザルツブルグの廃坑となった塩坑に枯れ枝を投げ込むとそれが2ヶ月後には白く輝く結晶となる。これは、次の過程をへて恋愛が結晶する。恋愛対象者にたいして「賞賛」、それが繰り返されて、「確認」にいたり、愛を得よう、あるいは得られるかなと「希望」が生まれ、恋人の美しさや性格に対して極端なまでに評価し、それに陶然となる。この課程を結晶作用と名づけた。 中央駅から歩いてザルツァッハ川を渡ってザルツブルグの中心街にでる。お土産店、宝石店、レストラン、カッフェが軒を連ねる。その近くにモーツァルトが住んでいた家が博物館になっていた。1756年にこの街で生まれたヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、小さいときから音楽の神童の評判が高く、父親、レオポルトは、彼を知らせるために、ミュンヘン、ウィーン、ミラノ、ローマなどに演奏旅行をした。当時のザルツブルグは,大司教領であり、父親はそこの副楽長であった。外国での就職活動に失敗したモーツァルトはザルツブルグの大司教の下でつとめることになる。外国への演奏旅行などによってヨーロッパの各地を回って広い世界を知ったモーツァルトには、狭い、息苦しい大司教領での音楽活動に飽き足らず、大司教の目には反抗的と思われ1781年に解雇される。そしてそれ以後ウィーンに定住する。演奏会、レッスン、オペラその他の作曲で生計を立てる。翌年、コンスタンツェ・ヴェバーと結婚する。モーツァルト博物館にはコンスタンツェとの生活で使った家庭の道具が陳列されていた。ウィーンでの生活は最初は順調だったが、モーツァルトの浪費癖もありじょじょに生活が苦しくなり1791年、貧困のうちになくなる。 ザルツブルグは1800年にナポレオンによって占領され、ナポレオンの力が弱くなるとバイエルンの一地域となり、そしてついにハプスブルグ帝国の領土となった。モーツァルトの妻コンスタンツェは、外交官ニコラウス・ニッセンと再婚し死後評価の高まったモーツァルトの楽譜や手紙を整理した。そしてザルツブルグにニッセンとともに住むことになる。 2011年9月20日 トーマス・マンは、北ドイツのリュ−ベックに生まれたが、1893年ミュンヘンに移った。山本定祐氏は、「世紀末のミュンヘン」において特にシュヴァービングでユートピアの夢の実現に向かっていった人たちを描いている。古代ギリシャのアテネ、ルネッサンス期のフィレンツェと同様に1900年前後の魅力の地、ミュンヘンに集まった人たちの物語を述べている。ミュンヘン大学の近くのこの地区にシュテファン・ゲオルゲ、リルケ、カンディンスキーなどのほかに、トーマス・マンも狭い小路の屋根裏部屋でブッデンブローグ家の人々を書いていたという。ここには1900年頃にマイヤーと名乗るロシア人がシュヴァービングの一画、カイザー道りに住んでいてレーニンという筆名で帝政ロシアの打倒のための機関紙を発行していた。レーニンが去ったあとトロッキーも一時ここにいたという。トーマス・マンは、これらの人々のようにミュンヘンであるユートピアを実現しようと考えたわけでないであろう。家族がミュンヘンに移ったので彼もそれに合流したのであろう。しかし感受性豊かなトーマス・マンは、1901年「ブッテンブローク家の人々」完成させた。この作品は広く読者を集めさまざまな言語に訳されるベストセラーになった。そして1905年ミュンヘン大学に務めるユダヤ系の数学教授の娘で当時学生だったカタリーナ・ブリングスハイムと結婚する。ミュンヘンとトーマス・マンの関係に関していえば彼は文学的名声となる作品をここで書いたが、ミュンヘンには家族が住み着いたから来たのである。ルートヴィヒ1世が検閲を廃止して自由なミュンヘンに寄与したことが遠因となって、大勢の芸術家などを中心とする優れた人が自らの意志で集まったのに対してトーマス・マンは、たまたま家族がリューベックからミュンヘンに移ったためにここに住んだのである。しかし彼はここ、ミュンヘンでカタリーナ・ブリングスハイムと知り合い結婚する。私は、ドイツ人の知り合いに案内されてイーザル川河畔の立派な家であるトーマス・マンの旧居を眺めた。彼は「ブッテンブローク家の人々」などが評価されて1929年にノーベル文学賞を受賞する。トーマス・マンは、ナチス政権を批判し、亡命し、ドイツにおける財産は没収された。 2011年9月09日 ルートヴィヒ1世、マクシミリアン2世とヴィッテルバッハ家の学問や芸術が好きな王が2代続き、次の王はルートヴィヒ2世であった。このバイエルン第4代国王が即位したのは、1864年18歳のときであった。彼は美しい容姿をしていたが父のマクシミリアン2世が買い入れたシュヴァンシュタイン城を好んだ。なぜならばこの城にはヴィッテルバッハ家の先祖の肖像とともに中世の聖杯伝説や騎士物語の主人公が描かれていて、白鳥の騎士、ローエングリーンには熱中した。これは15歳のときミュンヘンで上演されたワーグナーの歌劇「ローエングリーン」を見てとくに著しくなった。ルートヴィヒ2世は王位につくとワーグナーに面会を求めた。リヒャルト・ワーグナーは天才であったが浪費癖があり、当時借財に苦しんでいた。ルートヴィヒ2世はワーグナーに援助を申し入れた。その結果、ワーグナーはシュタルンベルク湖畔のベルク城近くに住むことになった。翌年、「トリスタンとイゾルデ」宮廷劇場にて演じられる。そしてワーグナーのオペラから取った絵を、壁画としてノイシュヴァンシュタイン城の居間には「ローエングリーン」書斎には「タンホイザー」、寝室には「トリスタンとイゾルデ」を描かせた。しかしワーグナーのためやいくつもの城の建設にバイエルンの財政を傾けさせたため、廃位させる試みが進み、その結果1886年ベルク城のそばの湖で溺死体となって発見される。ミュンヘンに留学していた森鴎外は「原田直次郎」をモデルとして「うたかたの記」にルートヴィヒ2世の死を入れている。 2011年8月31日 バイエルン王マクシミリアン1世のあとを継いだのがルートヴィヒ1世である。ルートヴィヒ1世は、学問や芸術を愛した。ドイツ各地や外国から、学者や芸術家を招いた。ミュンヘンを流れる河にイーザル河があり、この名前はケルト人に由来するという。
ルートヴィヒ1世は古代ギリシャにあこがれ、イーザル河畔のアテネが理想であったという。かれら芸術家たちがルートヴィヒ1世の招聘に応じたのは、1825年に全ての印刷物の検閲を廃止したことも大きな理由の一つであろう。このときはナポレオン戦争が終わり、ウィーン会議では、オーストリアの宰相メッテルニヒが中心となりフランス革命以前に戻すという正統主義がウィーン会議の中心の思想になった。 2011年8月29日 ミュンヘンに戻る。ミュンヘンはバイエルン州の州都でドイツの各州の中でも独特なアイデンティティーを持っている。ドイツ語圏の中でハプスブルグ家、ドイツ統一のイニシアチブを取ったプロイセンと並んで、長い歴史を通じて、ドイツを構成する諸国の中で持続性のある地域がバイエルンである。 ナポレオン戦争が終結し、1818年に憲法が制定されてマクシミリアン1世が 初代の王として即位した。そのあとを継いだのがルードヴィヒ1世である。彼は学問、芸術を愛した。ミュンヘン大学は18学部、学生数4万5000人弱であるが、その正式名称はルードヴィヒ・マクシミリアン大学である。この大学はランズフートにあったがルードヴィヒ1世によってミュンヘンに移された。 ミュンヘン大学の東側に王の名前のルードヴィヒ通りがあり、北に進むと凱旋門がある。その西に、大学の隣であるが美術アカデミーがあり、凱旋門をさらに進むとポプラ並木のあるレオポルト通りとなる。レオポルト通りの西側に詩人のリルケやロシア人・画家のカンディンスキーが住んでいたという。 レオポルト通りを東に行ったところにイギリス庭園がある。その側にミュンヘン市の若い男女の結婚の登録所があり、新郎新婦が親戚や友人に囲まれて祝福されているのをみながら庭園内の湖に行き、休憩した。 2011年8月22日 ゲッティンゲン大学の正式な名前はゲオルク・アウグスト大学でこれはハノファー選帝侯ゲオルク2世アウグスト〈イギリス王ジョージ2世〉の名前にちなんだ名前である。1734年に新設され、数学、物理学、法学、哲学において実績がある。この大学の教授としてグリム兄弟が招かれたのは1829年であった。 8月1日この大学町を訪れる。静かなたたずまいの町で前日は雨が降っていて涼しかったが、晴れて暑いくらいであった。大学附属の植物園は無料でさまざまな植物やきれいな花々が咲いていた。この大学からドイツでは最大の40名以上がノーべル賞を受賞している。 グリム兄弟のほかにこの大学で教えた人には数学者のガウス、哲学では、エドムント・フッサール、物理学ではハイゼンベルグなどがいる。ゲッティンゲン大学で博士号を得た人は市庁舎前のガチョウを連れた娘リーゼルの銅像にキスする風習がある。この大学は数学、物理学、天文学などに実績があるからか地動説のミコワイ・コペルニクスの生まれた街ポーランドのトルンと姉妹都市になっている。駅から大学への街路にそれが書かれたプレートがあった。 2011年8月18日 ミュンヘンの友人、K・マイヤー君のところに行った。彼はミュンヘン市役 所で福祉の仕事を担当している。彼は、休暇が取れたので彼の友人P・ジルバ ー氏がヘルツベルグにいるので行ってみないかと彼から誘いを受けた。ヘルツベルグはいわゆる過疎の町で人口が減っていて何とかそれに打ち勝ちたいと努力しているという。ハノバー空港で待ち合わせ、列車でヘルツベルグに行った。私がヘルツベルクに行きたいと考えたもう一つの理由は、その近くにゲッティンゲン大学があり、そこを訪ねたかったことである。カッセルはゲッティンゲン大学の近くにあり、距離的にいうとヘルツベルクとカッセルのほぼ中間がゲッティンゲン大学の所在地である。カッセルというとあのグリム童話で有名なグリム兄弟が長年住んだところであり、その近辺の人々から世代から世代えと語り伝えられたメルヘンを採集したのである。 ヘルツベルクについて1泊し、翌日、K・マイヤー君とP・ジルバー氏とヘルツベルクの市長に会った。市長の話では、この町は以前には1万7千人の人口があったが今は1万5千人に減少しているという。だから家があまっていて100万ユーロ以下で買えるという。ジルバー氏は、エスペラント語が話せ、市長にへルツベルグをエスペラントの都市にして世界各国からこの町に来てもらったらどうですかと提案してそれが採用された。近くに、ハルツ山地があり、国立公園になっている。ポーランドの女性が移り住み、近くに大きな建物を買い山にくる観光客やエスペラントを話す人を対象にホテルを計画をしている。またハンガリーからもここに永住する人の例があるという。 2011年8月10日 古代ギリシャ人が作ったのは現在われわれが考えるような国家ではなかった。現在のような国家ではなく、それぞれが独立した都市国家、すなわちポリスであった。だからそれぞれが法律や軍隊をもっていた。古代ギリシャ人は、今のギリシャにだけに住んだのではなく、現在のトルコやブルガリアまたエーゲ海の島々、すなわちロードス島やキプロス島にも居住した。また北アフリカやフランス、イタリアにも植民地を作った。そのような所に安全に船が発着できる場所を見つけ、建物と都市あるいは村を持つポリスを作った。紀元前1500年頃ギリシャ人が最初に住みついた地域は、狭く、山が多かった。紀元前750年頃になると、新しい都市や村を作る場所がもうなかった。そして食料も不足し始めた。そのためにたくさんのギリシャ人が生活のための新しい場所を求めて、移動をはじめ、ギリシャ人世界の拡大をもたらしたのである。エーゲ海地帯は非常に航海がしやすかった。とくに夏は、極度に乾燥して空気が澄んでおり、非常に遠くまで見通すことができ、航海者は島影を失うことなく航行できた。このため貿易は発達したのである。古代ギリシャ人の作った植民地は、イギリスのアメリカ大陸やインドなどに展開した本国に従属する植民地ではなく、独立した都市国家であった。
この植民地をたくさん造ったことと貿易の発展が知識を集積させ、また天文的知識や地図作成に役立ったと考えられる。日食を予言したミレトスのタレースは自然哲学の祖として知られているが、タレースは一説によれば貿易に携わったことがあるという。ピタゴラスや原子論のデモクリトスもイオニアの出身である。江上波夫・伊藤俊太郎の「文明移転」によればピタゴラスの定理も紀元前1800年頃のバビロニアの楔形文字の粘土板の中で使われているという。しかし証明はない。証明はギリシャ人が始めたという。オリエントでは王と一部の知識階級が知識を独占していたが、ポリス国家のギリシャでは対等の市民が議論をしながら知識の展開が図られ、原理、公理という証明の体系が作られた。
2011年7月8日 ルーマニアはかってローマの属州であった。そのためルーマニア人は、ローマ人の子孫であることを誇りとし、それを表すのがローマ人の土地を意味する「ルーマニア」という国名である。セルビア、ウクライナ、ブルガリアとルーマニアと国境を接する国々の多くは、スラブ系の言語が話されている。(旅の情報百貨店2F「ヨーロッパの常識」参照)だからルーマニアは、スラブという海の中のラテンの島のような存在である。 ルーマニアの言葉はローマ帝国の首都があったローマの言葉、イタリア語、かって外交の言葉といわれたフランス語、中南米に広く話されるスペイン語と同じ系統のラテン語族である。ところがこれらの国々の宗教はカトリック教である。 ルーマニアはカトリック教ではなくギリシャ正教である。カトリックとギリシャ正教が分かれたのは、ローマ帝国の分裂に関係がある。313年にローマ皇帝コンタンスタンティヌス1世によって公認されたキリスト教は、380年ローマ帝国の国教となった。ところが395年東西に分裂した。東ローマ帝国の首都はコンスタンティノーブルに、西ローマ帝国の首都はローマにおかれた。それぞれの首都にキリスト教の総主教座がおかれ、ローマ教皇は、西ヨーロッパ諸国、コンスタンティノーブルの総主教は、現在のギリシャ、トルコ、ブルガリア、ルーマニア、ロシアまでを統括した。これらの国々は、ギリシャ正教を信じるようになり、ルーマニア人は、ローマ人の子孫としての誇り、すなわちラテン語族に属するが、カトリック教ではなく、アジア的要素がより濃いギリシャ正教を信じる人が多くを占める。 2011年7月4日 モンゴルの世界征服の一環として鎌倉時代に文永(1274)・弘安(1281)の役という日本への蒙古の来襲がある。2回とも、ちょうど台風の時期で神風が吹いて日本軍は征服されないですんだという風に記憶している。今谷明氏の「封建制の文明史観」によれば文永の役は準備不足もあったが、弘安の役は鎌倉武士の士気は高く、蒙古軍の上陸を阻止するための石塁を築いていた。また海上輸送の条件は悪く、継続的補給計画がない蒙古軍の日本への上陸は神風がなくとも不可能と見ている。モンゴル軍は中国やペルシャのような官僚制が行きわっていた地域や建国から時間がたっていないポーランドなどの東欧諸国に対しては、簡単に蹂躙した。モンゴル軍は、クラクフまでは行くところ敵なしであったが神聖ローマ帝国領(ドイツ)のリーグニッツ(現在はポーランド領)の戦いではハインリヒ?世は戦死した。しかしブレスラフ、リーグニッツ、オルミュッツ、ノイシュタトの諸城は、陥落しなかった。もう一つ、中東のエジプト(パレスティナ)も蒙古軍に強く抵抗して征服にはいたらなかった。これらの地域はいずれも、封建制の下にあったことである。封建制は、反民主主義のイメージがあるがルネッサンスや近代化はこの地域から発生したという。
近くにアウシュヴィッツがあるクラクフの聖マリア教会は、クラクフの中心地、織物会館のある中央市場広場にそびえている。1222年に造られたが、1241年にモンゴル軍がクラクフを襲ったとき、敵が来たことを告げるラッパが吹き鳴らされた。ラッパの吹き手は、モンゴル軍の矢により殺された。それを記念して今でも1時間ごとに教会の塔の上のラッパが吹き鳴らさてれる。 2011年6月30日 ドロクロワによって描かれたフレデリック・ショパンの肖像画はルーブル美術館にあり1838年に製作されました。ドロクロワは、ジョルド・サンドとショパンの共通の友人であり、ロマン派の中心的画家で「民衆を導く自由の女神」などで有名です。ジョルド・サンドは「愛の妖精」などの作品を発表し、自由奔放で男装し、血筋的には貴族の一員であったが共和主義に傾倒しました。この年サンドとショパンは、二人の愛とショパンの健康のためにスペインのマジョルカ島にサンドの息子のモーリスと娘のソランジュの4人で行きました。 ルーブルにあるショパンの肖像画はピアノを弾いており、このルーブル美術館にはないが、その後ろにジョルド・サンドがいて演奏を聞いていたという。サンドの肖像画は今はコペンハーゲンのオードロップゴー美術館にあります。このショパンとサンドの肖像は誰が何のために切断したかは「なぞ」とされています。推測では三つの説があり、 ? 肖像画を手にしていた収集家が死亡し遺産相続で争いが起き切断された ? サンドの息子のモーリスがショパンを嫌っていて彼が切断させた ? もう一つは単に高く売るために二つに切ったという説である。 どれが正しいか今となっては「なぞ」だという。2011年6月25日 人間の本質は、自分が物事の当事者になることです。別の言葉で言えば、決定すること、あるいは決定の一部に参加することです。
当事者として関われば、あるいは決定するか、参加すれば、研究心も涌き、意欲も高まります。しかしもう一つの側面があります。それは優れた人に従えば、より良い実績が短期間にあげられることです。これは自分が決定することと矛盾します。しかし優れた人に盲従するのではなく、アドバイスとしてその意見を活用すればこの矛盾は解決されます。 2011年6月23日 ヨーロッパが近代を切り開いたのであるが、そのために重要なのが科学革命であり、宗教改革である。科学革命は天文学と関係が深い。ケプラー、ガリレオが大きな役割を果たしそれを総合したのがニュートンである。 この17世紀の科学革命を先導したのがニコラウス・コペルニクス(ポーランド名、ミコワイ・コペルニク)である。彼は1543年「天体回転論」という著書で地球などの惑星は太陽のまわりを回転していることを論じた。当時、ギリシャのアリストテレスの天動説は絶対的に信じられていた。聖書にも天動説が正しいと書かれていると信じられていた。当初は数学上の計算とか、天体の運動との関係から、難しい問題でありあまり非難されなかった。しかし反対の声はだんだん多くなっていった。ローマ・カトリック教会は、もちろんであるが、カトリックに反対して生まれたプロテスタント側からも、地動説反対の声が強く上がった。 ルッターは激怒し、カルビンは、聖書の権威をないがしろにするものと非難したという。それだけ衝撃が強かったのである。なお、1979年教皇ヨハネ・パウロ2世は、地動説を認めた。 2011年6月16日 チェコのプラハを訪れる人はかならずこの橋を渡る。下を流れるのはヴルタヴァ川である。水鳥がいて周りの景色はすばらしい。
プラハのカレル橋を渡った時,ガイドは英語でこの橋を説明した。チャールズ・ブリッジとときどき聞こえるがガイドブックで知った名前は、カレル橋だったのでおかしいなと思った。この石橋は神聖ローマ皇帝のカール4世の1357年に建設が始まり1400年に完成している。カール4世は1346年父ヨハンの後をついでボヘミア王カレル1世となっている。
ボヘミアというのは今のチェコであり、カレルはチェコ語である。1347年にドイツ王になるがドイツ 語ではカレルは、カールであり、エスペラント語では(Karlo/カルロ)である。英語ではカレルはチャールズなので、私は最初理解できなかったが、カレル橋はチャールズ・ブリッジである。ヨーロッパでは、固有名詞でこのようなことにしばしば出会う。例えばオランダ画家で日本人の間でとくに人気があるフェルメール(Vermeer)は英語ではヴァーマーと発音されるので英語で話す場合は注意が必要である。 2011年6月12日
2011年6月6日 「人魚姫」「マッチ売りの少女」「みにくいアヒルの子」などで知られているハンス・クリスチャン・アンデルセンは1805年デンマークのオーデンセに生まれた。家庭は貧しく、父は靴屋だった。11歳のとき父をなくし、中学を中退し、オペラ歌手になろうとコペンハーゲンに出るが失敗したが、後援者のおかげで大学に進むことが出来た。ヨーロッパ各地を旅行し、1834年にはローマに行っている。このときの経験が翌年、小説「即興詩人」となって結実し成功をおさめる。その同じ年の1835年はじめて、童話を書くが、最初は、彼は小説ほど重要視しなかった。しかしその後、アンデルセンの童話は、非常に評判となり世界中の子供から歓迎されている。 第1時世界大戦は、セルビア人の青年がサラエヴォでハプスブルグ帝国(オーストリア・ハンガリー二重帝国)のフェルディナント大公夫妻を暗殺したことから始まった。ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエヴォは、ボシュニャク人(ムスリム)、セルビア人、クロアチア人が混在して居住し、彼らは言語は同じだが、イスラーム、ギリシャ正教、カトリックといった宗教が異なる。 このように歴史から生み出された複雑な要素持った地域であるサラエヴォはユーゴスラヴィアに属していた。旧ユーゴスラヴィアは、チトーがナチスと戦い優れた戦略で打ち勝ち、戦後ユーゴスラヴィアとして独立した。チトーは、クロアチア出身であったが、ナチスとの戦いに際し、さまざま民族を平等に取り扱った。1974年に新しい憲法が実施されるが6共和国と2自治州が平等の立場に置かれた。 1980年チトーが亡くなり、1989年に東欧革命が起き、1党独裁の社会主義政権が終わり、複数政党制になるとセルビアでは、大セルビア主義をかかげる、スロボダン・ミロシェヴィッチが大きな力を持つようになる。権力を握ると、コソボ自治州から自治権を奪い、ハンガリー人が多数住む、ヴォイヴォディナ自治州も同様にする。これはチトーの各民族の平等の74年憲法からかけ離れていたため、1991年スロベニア、クロアチアが独立を宣言する。スロベニアとユ−ゴスロビア連邦軍の戦いは、短期間で終わるがクロアチアとは1995年まで続く。1992年ボスニア・ヘルツェゴビナも独立を宣言、セルビア人とボシュニャク人、クロアチア人が対立し、民族浄化、大量虐殺が起こる凄惨な戦争となった。NATOもこれに介入した。1995年アメリカのデイトン空軍基地でデイトン合意が調印されボスニア内戦は終わる。なおマケドニアは戦争なしで1991年に独立した。2006年モンテネグロ、2008年コソボも独立を宣言する。このように旧ユーゴスラビアは解体する。この地域は、東ローマ帝国、オスマン帝国、オーストリア・ハンガリア帝国に支配されたことがあり,またロシアやナチス・ドイツ など大国の利害が衝突する場所であったため、民族、宗教、言語が複雑に絡み合って理解するのに難しい地域である。 EUには27の国が加盟し、公用語が23ある。EUの前身、欧州経済統合体、欧州原子力共同体などに最初から参加していたのがオランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、フランス、西ドイツ、イタリアである。この中で、西ドイツ はドイツ語が話される中心的な地域であるが1990年東西ドイツ が統合されEU内でのドイツ語を話す地域が拡大し人口も増えた。ドイツ語を公用語としている国は6カ国ある。ドイツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、ベルギー、ルクセンブルクである。EUの18%の人々がドイツ語を話している。EUでは、あらためてドイツ語圏の人口が多いことに気がつく。 免罪符を買わせることなどのカトリックの行為に抗議するというプロテスタントがルターによって1517年に始まった。いわゆる宗教改革である。ルターの考えを支持したのは北ドイツ 、スウェーデン、デンマーク、オランダ、イギリスであった。ハプスブルグ家は、カール5世のときその統治する領域は最大となった。ハプスブルグ家は神のご加護で発展したと代々信じ、カトリックを強く支持してきた。カトリック側には南ドイツ 、オーストリア、スペインなどがつき、プロテスタントとカトリックの30年戦争が起こった。ブルボン家のフランスは、カトリックであったがハプスブルグ家と敵対関係にあったため、プロテスタント側についた。ドイツ語を話す地域だけ、2つの陣営に分かれたわけである。30年戦争はドイツ を荒廃させ、その結果長く分裂の状態が続いた。フランスやイギリスのような中央集権体制が進まず、諸侯の領土の集合にすぎなかったためドイツ統一が遅れた。ビスマルクがプロイセンの宰相となり、オーストリアと戦い勝利して統一が達成された。 ヨーロッパの冬は長い。だから春の訪れは非常な喜びである。春を象徴する花がチューリップである。チューリップといえば、オランダを思い出すであろう。ヨーロッパ各国をテーマとするカレンダーには、オランダのチューリップが必ずといってよいほど出ている。オランダにはかってチューリップバブルということがあった。オランダでチューリップの人気が異常に沸騰したことがある。1570年頃にはチューリプ人気が高まり、金持ちは高い値段で争って購入した。1636年にはアムステルダム証券取引所で定期市が設けられるようになった。非常な高値がつき、あらゆる階層の人が夢中になった。しかしある人がチューリップの値段の異常に気づきこのバブルは終わりとなった。どうしてこんなに人気がでたであろうか? チューリプの球根はイスタンブールから取り寄せられた。イスタンブールは当時トルコの首都であった。チューリップの語源は、ターバンである。1453年オスマントルコは、東ローマ帝国を滅ぼした。東ローマ帝国の首都名はコンスタンチノープルであった。この名前はローマの皇帝であり、キリスト教を公認したコンスタンチヌス帝に由来する。オスマン帝国は名前をコンスタンチノーブルからイスタンブールに改名した。当時、先進国であったトルコ帝国の美しいチューリップは、ヨーロッパの人々を強く魅了したのである。オランダ人は、このチューリップバブル事件にもかかわらず、チューリップを愛好し、今はチューリップを世界に輸出している。
|
 旅のつれづれ草(20)
旅のつれづれ草(20)





 古代ギリシャ人の殖民活動と貿易
古代ギリシャ人の殖民活動と貿易

 スラブの中のラテンの国―ルーマニア
スラブの中のラテンの国―ルーマニア 旅のつれづれ草(11)
旅のつれづれ草(11)